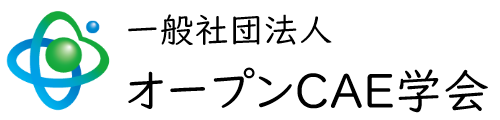トレーニング
- オープンCAEに関するトレーニングを開催します.
- 参加には,シクミネットによる参加登録が必要です.
- 日本機械学会計算力学技術者認定受験資格の認定証の取得希望の方は,熱流体の1・2コマ目を連続して受講する必要があります.
日時
- 2024年11月7日(木) AM9:30〜 受付開始,講習時間 10:00-17:35
場所
- シンポジウム会場: 九州大学 椎木講堂 第3・4・5講義室(〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744)
- 会議室での対面式トレーニングを基本とし,希望者にはオンラインでの受講も可能なハイブリッド開催となります.オンラインではタイムリーなサポートが困難なことから,質問時間での回答など必要最低限のサポートのみになります.講習概要を確認し,サポートが必要と思われる方は現地参加をご検討ください.
- A1:"オープンCAEのための高性能計算入門"は現地開催のみです.特別無料講習のため,オンライン配信は行いません.参加者数確認のため,参加申込はしてください.
タイムテーブル
| 時間 | トレーニングA(第4講義室) | トレーニングB(第3講義室) | トレーニングC(第5講義室) |
| 09:30 - 10:00 | 受付 | - | - |
| 10:00 - 11:45 | A1:オープンCAEのための高性能計算入門 講師: 大島聡史(九州大学) [配信無しの現地開催のみ, 無料] |
(午前はAコースのみ実施) | (午前はAコースのみ実施) |
| 11:45 - 12:45 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
| 12:45 - 14:15 | A2: OpenFOAM講習(入門)-OpenFOAMによる熱流体シミュレーション入門 講師: 中川慎二 (富山県立大学) | B2:Modelicaによるマルチドメイン(電気・磁気・機械・熱)シミュレーション基礎 講師: 西 剛伺 (足利大学) | C2:大規模並列 OpenFOAM 入門 講師: 小林泰三(九州大学) |
| 14:15 - 14:25 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
| 14:25 - 15:55 | A3:OpenFOAM講習(初級)-OpenFOAMによる熱流体シミュレーション初級 講師: 中川慎二 (富山県立大学) | C3:codedFixedValueを使うOpenFOAMの初級プログラミング 講師: 田村守淑 (オープン科学計算コンサルティング) | |
| 15:55 - 16:05 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
| 16:05 - 17:35 | A4:DEXCS-OpenFOAM 2024の歩き方 講師: 野村 悦治 (OCSE^2 ) | B4:粒子モデル破壊解析ツールPeridigm入門(入門〜初心者向け)講師: 柴田良一(岐阜高専) | C4:PyVistaを使ったオープンCAEの可視化 講師: 川畑真一 (オープンCAE勉強会@関西) |
講習内容
本トレーニングの講習内容をご紹介します。
- A1:オープンCAEのための高性能計算入門(特別無料講習・座学のみ)
- 講師:大島聡史(九州大学)
- 講習概要:オープンCAEにも役立つ高性能計算の基礎知識についての講習会を行います. 個人PCでも簡単に試せるOpenMPやMPIを用いた並列化プログラミングから,パブリッククラウドやスーパーコンピュータの活用法まで,オープンCAEに役立ちそうな話題を広く浅く扱う予定です.本講習会は特別講習として無料で実施しますので,興味のある方はお気軽にご参加ください.
[本講習は現地開催のみで, 配信はありません] - 準備:特にありません.
A2:OpenFOAM講習(入門):OpenFOAMによる熱流体シミュレーション入門
- 講師:中川 慎二 (富山県立大学)
- 講習概要:密閉容器内の自然対流を例にとり,OpenFOAMを使ってソルバの選択から結果の可視化までの一連の流れを体験します.本コースに合わせて,引き続き初級コースを受講することで,日本機械学会計算力学技術者熱流体分野初級認定申請資格・2級受験資格が得られます.なお本講習では講師はオンラインにて講習を行いますが, 現地参加の方は現地サポートメンバーがサポートを行います.
- OpenFOAM-v2406と講習用例題などを含んだ仮想マシン・アプライアンスを配布します.参加登録完了後に参加者向けに事前にお知らせするリンク先から仮想アプライアンス (OVAファイル) を入手し,仮想環境Virtualboxなどへインポートしてください.これにより,講習会用仮想マシンが起動できることをご確認ください.参加登録前の動作確認用の仮想マシン・アプライアンス(資料など含まない)は,こちらから取得できます.
A3:OpenFOAM講習(初級)-OpenFOAMによる熱流体シミュレーション初級
- 講師:中川 慎二 (富山県立大学)
- 講習概要:入門コースを受講された方を対象に,密閉容器内自然対流の例題を使って,実験結果との比較により妥当性を検討しながら,メッシュや境界条件への依存性について学びます.入門コースと合せて受講することで、日本機械学会計算力学技術者熱流体分野初級認定申請資格・2級受験資格が得られます.なお本講習では講師はオンラインにて講習を行いますが, 現地参加の方は現地サポートメンバーがサポートを行います.
- A2と同じ環境を利用します.
A4:DEXCS2024 for OpenFOAMの歩き方
- 講師: 野村悦治 ( オープンCAEコンサルタントOCSE^2 )
- 講習概要:DEXCS for OpenFOAM はOpenFOAMを「誰にでも簡単,すぐに使える」
を目的に開発されたオールフリー& オープンのオールインワンパッケージシステムで, 初心者向けの自習ツールとしての利用から始めて, これを使いこなせるようになれば実践的な解析環境としても利用で きるようになっている. 本講習では最新のDEXCS2024を使いこなす為の勘所をデモ 解説する. - 準備:DEXCS2024のシステムを各自のPCにダウンロードして, 事前にシステムが起動することを確認しておいてください. DECXS2024は統合ISO形式または分割形式でダウンロードできます. インストール方法はこちらをご参照ください.
(追加情報) DEXCS2024でKernelが更新されると, 立ち上がらなくなる不具合が生じています. KernelPanic の項目を参照下さい.
すでにダウンロードして, これからインストールする人は, 上記記事中(対策1)のインターネットに接続しないでインストールを, これからダウンロードする人は, 分割型の Kernelアップデート版 を利用(対策2)し, 対応をお願いします.
B2:Modelicaによるマルチドメイン(電気・磁気・機械・熱)シミュレーション基礎
- 講師:西 剛伺(足利大学)
- 講習概要:OpenModelicaはマルチドメイン対応のモデル記述言語Modelicaを用いてモデル作成,シミュレーション実行,結果の確認まで行うことのできるオープンソースツールです.
本講習では,モータの駆動を題材として, 電気、磁気、機械(主に回転運動)、熱の物理ドメインとそのモデル化について学ぶとともに、ハンズオン形式でモデル作成を体験頂きます.対象者は初心者向けです. - 事前準備:OpenModelica 1.22.x (Windows版、Official Release)以上を使用できる状態にしておいてください.
B3:PrePomaxによる定規のたわみ解析講師:荒木康宏(オープンCAE学会)講習概要:構造解析の初心者向けを想定し, 定規をたわませたときの変形解析をPrePomaxで行います. あわせて, 実測もおこない, 実験とCAEの計算結果の妥当性検証を行います. 解析にはWindows10またはWindows11の動作するPCとPrePomax ver2.00以降が必要なため事前の準備をお願いします.準備:オープンCAEWiki PrePoMaxのインストールに従ってご準備ください.なおPrePoMaxのダウンロードサイトはこちらです.
B3は都合により中止となりました.
B4:粒子モデル破壊解析ツールPeridigm入門(入門〜初心者向け)
- 講師:柴田良一(岐阜高専)
- 講習概要:粒子モデル破壊解析ツールPeridigmは, 有限要素方法などの連続体モデルによる構造解析ツールでは困難であった, 著しい破壊現象として破断や飛散を伴うような現象に対して, オープンソースツールでの数値解析を可能にします. これにより, 今回は入門的な内容として, WIndowsのWSL2で動作したUbuntuにおいて, 解析環境を構築して付属例題の実行をまでを講習します.
- 準備:今回は, Ubuntu(Linux)の操作を前提知識として, Peridigm解析環境を構築することを目的とします. Windows10/11のPCにおいて, WSL2を準備してUbuntu22.04を動作させ, ここに著者が用意したPeridigm導入ファイルを会場でUSBメモリ回覧して利用します. 事前準備は不要ですが, USBメモリが利用できるWindowsPCを用意して参加してください.
- C2:大規模並列 OpenFOAM 入門
- 講師:小林泰三(九州大学)
- 講習概要:スーパーコンピュータシステムのような大規模並列計算でOpenFOAM計算の効率化を行う方法について解説します.特に,パラメータサーベイや境界条件への実験値の適用などを,decompose, reconstruct を介さずに行う方法を解説します.これにより,大規模並列計算に必要なリソース(計算機資源と時間の双方)の削減を実現します.
- 事前準備:特にありません.受講者には講習で用いたツール(スクリプト類)を配布します.
C3:codedFixedValueを使うOpenFOAMの初級プログラミング解法
- 講師:田村守淑 (オープン科学計算コンサルティング)
- 講習概要:OpenFOAMの標準機能だけでなく, OpenFOAMでは課題に応じたプログラミングが必要な場合がありますが,OpenFOAM言語の習得は簡単ではありません.プログラミング初心者を対象に, 比較的に簡単なcodedFixedValue使った境界条件プログラミングを題材に基本的なOpenFOAM言語とそれに関連するC++について学習します. 非定常非一様境界条件や内部物理量による境界条件制御など,様々な境界条件のカスタマイズができるようになることを目指します. 内容理解の前提として,以下を満足していることとします.
- OpenFOAMの基本的な使用方法を知っている
- 何らかのプログラム作成経験がある
また, 学習内容は以下を予定しております.
① codedFixedValueを使うためのC++とOpenFOAM言語の解説と演習(elbow)
② codedFixedValueを使った非定常非一様境界条件設定の解説(elbow_parabolic)
③ codedFixedValueを使った境界条件の制御方法の解説(flange_control) - 準備:ご自身で環境設定する場合, OpenFOAMはESI版のOpenFOAM-v2106以降, Paraview, gnuplot をインストールした環境をご用意ください.または基礎編A2-A3の講習で利用する仮想マシンをそのまま,ご利用いただくことが可能です.トレーニングで使用するテンプレートファイル配布について後日, 受講者に詳細を連絡します.
C4:PyVistaを使ったオープンCAEの可視化
- 講師:川畑真一 (オープンCAE勉強会@関西)
- 講習概要:
PyVistaを用いてオープンCAEコードの結果を可視化しま す. PyVistaはPythonスクリプトの形でデータを可視化す るライブラリになります. Jupter Notebook上で動作させることにより、 インタラクティブに可視化を実施し, 実施した操作をPythonスクリプトとして残すことができます . 本講習ではOpenFOAMを対象として, 結果の可視化操作を通してPyVistaの使い方をご説明いたし ます. - 事前準備:PythonならびにJupyter Notebook, PyVistaのインストールをお願いします. 事前準備については受講登録者には詳細を別途ご案内します.